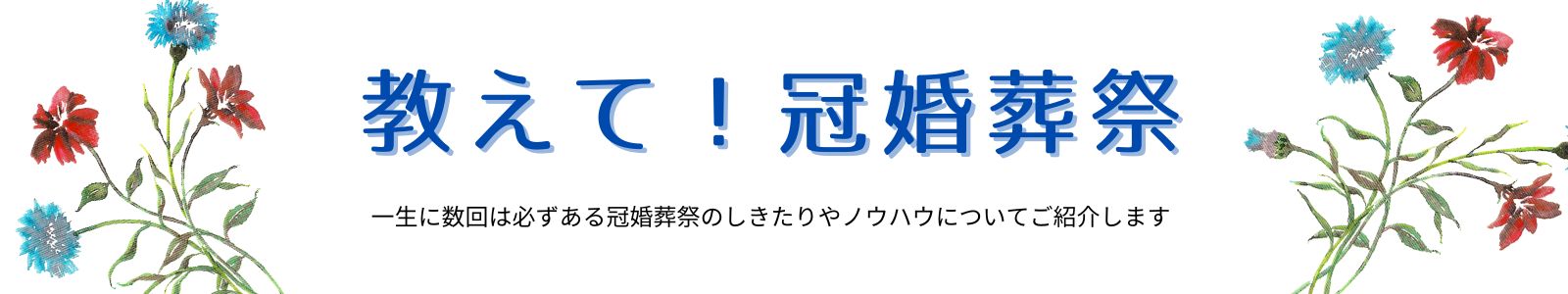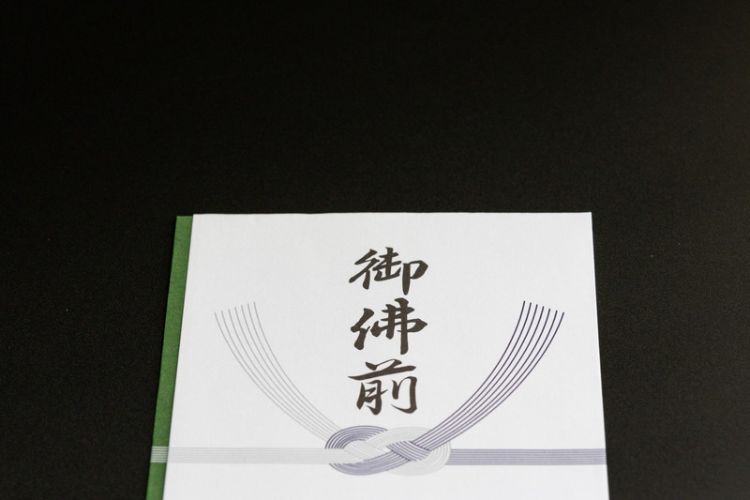葬儀は故人を偲び、最後のお別れをする場です。
しかし、遠方で駆けつけることが困難、子どもが小さくて置いて行けない、自分しかできない仕事を抱えている、出張中で帰ることができないなどの理由で、葬儀にどうしても参列できないという場合もあると思います。
そんなときに知っておくべきマナーについて解説します。
葬儀に参列できないとき、まずは一報入れよう

主催者から連絡をもらっても、葬儀に参列できないことがわかったら、まずは速やかに主催者に連絡しし、手短に哀悼の意と葬儀に参列できない旨を伝えましょう。
また、欠席の理由に具体的な内容を伝えることで相手に不快な思いを与えそうな場合は、「どうしても都合がつかず」「やむを得ない事情で」など具体的に理由の明言を避けても問題はありません。
香典の送付

葬儀に参列できない場合でも、香典を送ることは可能です。郵送や銀行振込などで送ることができます。
ただし、送付する際は、香典を入れる封筒に「御霊前」の文字とともに、自分の名前と住所を記入しましょう。
香典の相場は下記の通り
香典を送ろうと思った際、いくらくらい送れば良いのでしょうか?
香典の相場は、自身と故人や遺族との関係性、地域や宗教などにより異なります。一般的な金額は下記の通りですが、具体的な金額は周囲の習慣や自身の経済状況を考慮して決めることが重要です。
- 親族: 30,000円~100,000円
- 親しい友人・知人: 10,000円~30,000円
- 同僚・ビジネス関係: 5,000円~10,000円
- 近隣の人々: 3,000円~5,000円
また、香典は故人への敬意を示すものであり、金額だけが重要なわけではありません。心からの哀悼の意を込めて香典を捧げることが最も大切です!
弔電の送付
弔電を送ることも一つの方法です。
弔電は、葬儀の日時に間に合うように送ることが一般的です。
内容は簡潔に、故人への哀悼の意を述べる形にしましょう。
弔電は、電報屋のエクスメールなど、インターネット上で手配することができますので、利用してみてはいかがでしょうか?
忌み言葉とタイミングに気をつけて

その際注意しなければいけないのは、重ね重ねという言葉のように重ねるような忌み言葉を使わないのがマナーです。
香典を送ると香典返しなどをしなければなりませんから、それを気遣って香典を送らない場合は、花を送るのがいいでしょう。
この場合の時期としては、四十九日までに送るというのが一般的なタイミングです。
後日のお悔やみ

葬儀に参列できなかった場合でも、後日改めて故人の家族に対して哀悼の意を表すことができます。
訪問するか、手紙を送るなどして、故人への思いを伝えましょう。
急に訪れる冠婚葬祭!いざというときのために備えをしておこう

冠婚葬祭のタイミングは、突然やってくるものです。
特に葬儀の場合は予期せぬタイミングでやってくることが多いため、明後日告別式と言われたものの「服を用意していない」ということになりがちです。
急な弔辞でも慌てないように、前々からの購入をお勧めします。
冠婚葬祭のときには、気持ちも大事ですが、その気持ちを服装で表現することも、非常に大事なこと。
大事な場所であるからこそ、しっかりとした服装で臨みましょう。
また、すでにお持ちの方でも、年月が経つと体型の変化によってサイズが合わなくなっているなどの理由から、当日に着用できないことがあります。
数年に一度は、手持ちの礼服のサイズの確認をお勧めいたします。
そういったときに備え、当サイトでは、オススメのスーツ・礼服購入サイトを、いくつかご紹介させていただこうと思います。
葬儀のフォーマルや鞄などを一括で購入できるショップ
京都スタイル
レディース・メイズともにフォーマルウェアを始めバッグ・靴、数珠や帛紗など一通り販売しています。和装の喪服もあり。こちらでまとめて購入するのが簡単に揃えられそうです。
 ブラックフォーマル バッグ 日本製
ブラックフォーマル バッグ 日本製
このようなシンプルで定番のフォーマルバッグがあります。
 ブラックフォーマル レディース 喪服 女性 2点セット ワンピーススーツ
ブラックフォーマル レディース 喪服 女性 2点セット ワンピーススーツ
夏用のブラックフォーマルの販売もありますよ。
洋服の青山
スーツといえば、やはり洋服の青山などのスーツメーカーでしょう。
通常のスーツはもちろんのこと、ブラックフォーマルも多数扱っています。
 ブラック系 トートバッグ【撥水加工】
ブラック系 トートバッグ【撥水加工】
メンズの場合、あえてフォーマル用のバッグは販売されていないのですが、ビジネス用の黒いバッグを持っていくと良いでしょう。
 CHRISTIAN ORANI BLACK LABEL メンズ ブラックスーツ
CHRISTIAN ORANI BLACK LABEL メンズ ブラックスーツ
女性のフォーマルも扱っていますので、有名なお店の方が安心という方は青山がおすすめです。
弔電を送る際にはここがおすすめ!
電報屋のエクスメール
電報屋のエクスメールは、祝電・弔電など様々な電報を取り扱っています。
 弔電 お悔やみ電報 紙素材カード「白い百合」
弔電 お悔やみ電報 紙素材カード「白い百合」
シンプルな台紙であればメッセージ込みで1,540円。お財布を痛めずに気持ちを伝えることができます。また、16時までであれば翌日お届けが可能なところも嬉しいですね。
まとめ
葬儀に参列できないときでも、故人への敬意を示す方法はあります。
欠席の連絡、香典の送付、弔電の送付、後日のお悔やみなどを通じて、故人への思いを伝えることが大切です。何らかの形で故人を偲び、故人への敬意を忘れないようにしましょう。