胴吹き枝とは?幹に生える細い枝の役割と剪定のタイミング
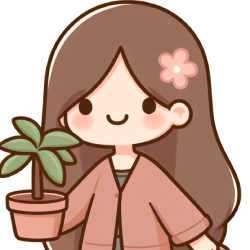
ガーデニングを始めたい
『胴吹き枝』ってどんな枝ですか?

ガーデニング研究者
幹の途中から出ている細い枝のことです。幹から直接生えているので、『幹吹き枝』とも呼ばれます。
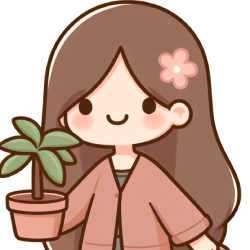
ガーデニングを始めたい
どうして胴吹き枝はよくないんですか?

ガーデニング研究者
胴吹き枝があると、養分がそちらに取られて、樹勢が弱まるからです。なので、胴吹き枝は取り除く必要があります。
胴吹き枝とは。
ガーデニングにおいて、「胴吹き枝」とは、幹の中間から生えてくる細い枝のことです。幹から生えてくるため、「幹吹き枝」とも呼ばれます。この枝を残しておくと養分が奪われ、木の勢いが弱まるので注意が必要です。
胴吹き枝とは何か

胴吹き枝とは、木本の幹や根元から直接発生する、細い枝のことを指します。基本的には、本来は枝が伸びるはずのない部位から発芽する枝であり、樹勢が強いときに発生しやすくなります。幹や根元から発生するため、幹吹き枝やひこばえとも呼ばれます。
胴吹き枝ができる原因

胴吹き枝ができる原因
胴吹き枝は、幹から直接生える細い枝のことです。大抵は葉が生い茂り過ぎたり、込み合ったりしている枝の付け根や、幹に傷がある箇所から発生します。光合成に必要な光を十分に得られなかったり、他の枝との競争に負けて弱った枝が、養分を求めて幹の方向に成長することで胴吹き枝が発生します。また、剪定が不十分だったり、枯れた枝を取り除かなかったりすると、胴吹き枝が発生しやすくなります。
胴吹き枝がある状態のメリットとデメリット

-胴吹き枝がある状態のメリットとデメリット-
胴吹き枝が存在すると、幹から直接成長する新しい枝が豊富になるため、次のような利点があります。
* 果実の生産量の向上胴吹き枝から新しい果実枝が育ち、果実の収穫量が増えます。
* 病害虫の軽減胴吹き枝から新しい枝が更新されるため、病害虫の発生率が低下します。
* 樹形の維持胴吹き枝を適度に剪定することで、樹のバランスを整え、適切な形に保つことができます。
一方、胴吹き枝が多い状態のデメリットもあります。
* 混み合った枝ぶり胴吹き枝が増えすぎると、枝が混み合い、風通しが悪くなります。
* 果実の品質低下枝が混み合うと、日当たりや通風が悪くなり、果実の品質が低下する可能性があります。
* 剪定の負担胴吹き枝が多いと、剪定作業が煩雑になり、負担が増えます。
胴吹き枝を剪定するタイミング

胴吹き枝を剪定するタイミングは、その状態や目的によって異なります。一般的には、以下の時期が適しています。
* 春から初夏(3月~6月頃) 樹勢が強く、枝が徒長しやすい時期。不要な胴吹き枝を間引き、樹形を整えたり日照を確保したりします。
* 晩秋から冬(11月~3月頃) 樹勢が弱く、剪定によるダメージが少ない時期。枯れた枝や混み合った枝を取り除き、翌年の樹勢を確保します。
胴吹き枝を剪定する方法

-胴吹き枝の剪定方法-
胴吹き枝を除去する際には、剪定バサミを使用し、幹から3~5mmほどを残して切り取ります。幹に傷をつけないように、根元に近い部分で切ることが重要です。また、切り口を斜めにカットすると、水の侵入を防いで腐敗を予防できます。胴吹き枝を取り除いた後は、切り口に癒合剤を塗布して保護しましょう。






