「とう立ち」ってなあに?
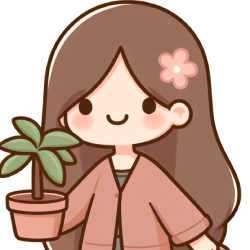
ガーデニングを始めたい
『とう立ち』という言葉の意味を教えてください。

ガーデニング研究者
花を着生する茎が伸び出すことで、抽苔(ちゅうだい)とも呼ばれます。
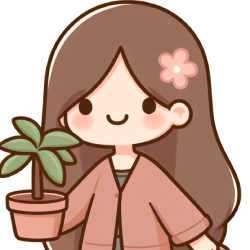
ガーデニングを始めたい
なるほど。何が要因なんでしょうか?

ガーデニング研究者
温度と日長の影響が大きいと言われています。
とう立ちとは。
ガーデニングでは、「とう立ち」という用語が用いられます。これは、花を咲かせる茎が勢いよく伸び出すことを指します。この現象は、「抽苔(ちゅうだい)」とも呼ばれます。とう立ちの原因として、気温や日照時間が大きく影響していると考えられています。
とう立ちとは何か

-とう立ちとは何か-
植物の「とう立ち」とは、花茎が急速に伸びて花を咲かせる現象のことです。主に葉野菜や根菜類で見られます。きっかけとなるのは、低温や日照時間の短縮など、植物にとっての「ストレス」です。
植物は、環境に適応するために「ストレス耐性物質」を生成します。この物質が花芽形成を促進し、とう立ちが始まります。キャベツやレタスなどの葉野菜では、軟らかい葉が硬くなり、苦みやえぐみが強くなります。大根やニンジンのような根菜類では、茎が伸びて根が固くなるので、食用としての価値が低下します。とう立ちが起こると、野菜本来の味が損なわれ、食感も悪くなってしまいます。
とう立ちの原因

-とう立ちの原因-
とう立ちとは、植物が茎を長く伸ばして花を咲かせる生理現象のことです。その主な原因は、環境条件の変化にあります。具体的には、日照時間の減少(短日長)や気温の低下といった外部要因が影響します。また、植物の遺伝的要因や栄養状態によってもとう立ちの発生が左右されます。
短日長が訪れると、植物は体内でジベレリンという植物ホルモンの合成が抑制され、青酸エチレンというガスの放出が増加します。青酸エチレンはとう立ちに関与する別の植物ホルモン(フロリゲン)の産生を促します。一方、低温は青酸エチレンの放出を抑制するため、とう立ちが遅れる場合があります。また、窒素過多などの栄養過剰状態では、植物の栄養成長が促進されてとう立ちが遅れることがあります。逆に、カルシウム不足などの栄養不足状態では、とう立ちは早まる傾向があります。
とう立ちを防ぐには

「とう立ち」を防ぐには、いくつかの方法があります。適切な環境下で栽培することがまず重要です。温度や日照時間が適している必要があります。また、栄養バランスの良い土壌で栽培し、適切な水やりを行ってください。とう立ちを誘発するホルモンであるエチレンガスを放出する植物を近くに植えないことも効果的です。さらに、適切な時期に収穫することも重要です。収穫時期が遅れると、とう立ちが起こりやすくなります。
とう立ちした野菜の活用方法

-とう立ちした野菜の活用方法-
とう立ちした野菜は、栄養価が低下し、繊維質が硬くなるため、生食には向かなくなります。しかし、廃棄するのではなく、工夫次第で再利用できるのです。
* -炒め物や煮物-
とう立ちした葉や茎は、炒め物や煮物に利用できます。繊維質が気になる場合は、細く刻んだり、長く煮込むことで柔らかくできます。
* -スープやミキシング-
葉や茎をスープに加えたり、ミキシングしてスムージーや野菜ジュースに利用できます。こうすることで、栄養価を摂取しつつ、繊維質の摂取を軽減できます。
* -漬物-
とう立ちした葉や茎は、ぬか漬けや塩漬けにすることで、歯ごたえを活かした漬物として楽しむことができます。
* -コンポスト-
とう立ちした野菜は、家庭のコンポストに追加できます。分解過程で土壌の栄養を豊かにする有機物になります。
とう立ちを活用する栽培方法

とう立ちを活用する栽培方法では、この現象の特性を活かした栽培法についてご紹介します。一般的な栽培方法では、とう立ちが発生すると花を咲かせて結実するため、野菜としての収穫量が減少してしまいます。しかし、とう立ちを利用した栽培法では、あえてとう立ちさせて花ではなく茎や葉を食用にします。
具体的には、レタスや白菜などの葉物野菜では、とう立ちが始まると茎が伸びて葉が厚くなります。この茎や葉は、シャキシャキとした食感とわずかな苦みが特徴で、炒め物やサラダ、漬物などに適しています。また、セロリやアスパラガスなどの茎菜では、とう立ちによって茎がより長くなり、太くなるため、収穫量を増やすことができます。このように、とう立ちという現象をうまく活用することで、野菜の収穫時期を延長したり、新たな食材として利用したりすることが可能です。






