庭のつぼ肥とは?作り方と効果を解説
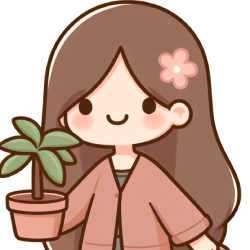
ガーデニングを始めたい
『つぼ肥』について教えてください。

ガーデニング研究者
『つぼ肥』は、樹木などの根元に肥料を施す方法です。樹冠の真下、つまり根が一番密集している部分に穴を掘って肥料を施します。
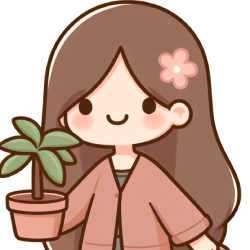
ガーデニングを始めたい
なるほど。根が一番吸収しやすい場所を狙って肥料を施すんですね。

ガーデニング研究者
そうです。樹木に効率的に栄養を与えることができます。定期的に行うことで、樹木の健康と成長を促進できます。
つぼ肥とは。
ガーデニングの用語「株元施肥」とは、樹木が密集して植えられた庭などで、肥料を施す方法です。樹木が最も栄養を吸収しやすいのは、樹冠と呼ばれる枝葉の真下です。このエリアには、細い根が集中しています。そこで、樹冠の真下を目安に数か所穴を掘り、そこに肥料を与えます。
つぼ肥とは?

-つぼ肥とは?-
つぼ肥とは、限られた空間内で生ごみなどを発酵させて作る有機肥料のことです。 大きな容器(つぼ)を使用し、生ごみや雑草、落ち葉などを積み重ねて発酵させます。発酵過程では、微生物がこれらの有機物を分解し、腐植土やミネラル豊富な肥料に変換します。つぼ肥は、緩やかに効くため、野菜や花などのあらゆる植物に適しています。また、土壌を改善し、保水力や通気性を向上させます。
つぼ肥の作り方

つぼ肥の作り方を理解することは、豊かな庭を作るために不可欠です。つぼ肥とは、有機材料を分解してできた堆肥のことで、土壌の健康を促進し、植物の成長を助けます。つぼ肥を作るには、まず「材料」を集めます。生ゴミ、落ち葉、刈り取った芝生、さらには木材の切屑などが適しています。次に、材料を層状に重ねていきます。窒素が豊富な緑色の材料と炭素が豊富な茶色の材料を交互に重ねるのがポイントです。水分を加えて、定期的にかき混ぜて空気を入れましょう。数か月から数年かけて、材料は分解され、富栄養な土壌改良剤であるつぼ肥となります。
つぼ肥の効果

つぼ肥の効果
つぼ肥は、土壌の健康を向上させ、植物の成長を促す優れた有機肥料です。その主な効果を以下に示します。
* -保水力と排水性の向上- つぼ肥は土壌に有機物を追加し、保水力を高めながら排水性を向上させます。これにより、植物に必要な水分が十分に供給され、根腐れを防ぎます。
* -栄養分の供給- つぼ肥には、窒素、リン、カリウムなどの必須栄養素が含まれています。これらの栄養素は、植物の健康的な成長と発達に不可欠です。
* -微生物の活性化- つぼ肥中の有機物は、土壌中の微生物の活動に栄養を与えます。これらの微生物は、栄養分の分解や土壌構造の改善に関与しています。
* -病害虫の抑制- つぼ肥は、土壌のpHバランスを整え、病害虫の発生を抑えるのに役立ちます。健康な土壌は、病原菌や害虫に対する植物の抵抗力を高めます。
* -土壌の構造改善- つぼ肥は、土壌構造を緩め、通気性を向上させます。これにより、根が深く伸び、植物が安定して生育できます。
つぼ肥に向いている肥料

-つぼ肥に向いている肥料-
つぼ肥を作るためには、適切な材料を使用することが重要です。適した材料として以下が挙げられます。
* -生ごみ-野菜くず、果物くず、コーヒーかすなどの有機物。
* -枯れ葉-窒素が豊富で、つぼ肥に嵩増しをします。
* -生芝-窒素が豊富で、発酵を促進します。
* -鶏糞-窒素、リン酸、カリウムを豊富に含んでおり、つぼ肥に栄養価を与えます。
* -牛糞-窒素が豊富で、土壌を改良します。
つぼ肥の時期と頻度

つぼ肥の時期と頻度
つぼ肥を作る時期は、家庭から出る生ごみが多い夏場が適しています。この時季には、野菜の皮や果物のヘタ、茶葉などの有機物が豊富に手に入ります。また、定期的につぼ肥を作ることが大切です。一般的に、2~3カ月に1回の頻度で作るのが理想的です。そうすることで、発酵が継続し、常に新鮮なつぼ肥を得ることができます。ただし、あまり頻繁に作ると発酵が進みすぎて栄養価が低下してしまうので注意しましょう。






