ナシやボケにできる『赤星病』
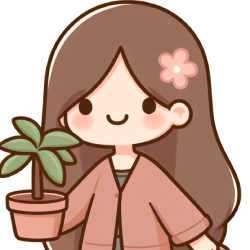
ガーデニングを始めたい
先生、『赤星病』について教えてください。

ガーデニング研究者
『赤星病』は、ナシやボケの葉の裏に茶褐色の斑点が出る病気です。冬の間はビャクシン類に寄生するので、それらの樹種を近くに植えないようにすることが予防策になります。
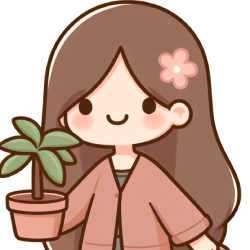
ガーデニングを始めたい
冬にビャクシン類に寄生するんですか?

ガーデニング研究者
そうです。ビャクシン類は『赤星病』の越冬場所になるのです。そのため、ナシやボケの近くにビャクシン類を植えると、病気が発生しやすくなります。
赤星病とは。
赤星病は、ナシやボケの葉の裏側に茶褐色の円形斑点ができる病気です。冬になると、カイヅカイブキやビャクシンなどのヒノキ科の樹木に移行します。このため、ナシやボケとヒノキ科の樹木を近くに植えることは避ける必要があります。
赤星病とは?

「赤星病」とは、リンゴや梨、ボケなどのバラ科植物に発生する病気です。病原菌が植物の果実や葉、枝、幹に寄生し、赤褐色の斑点や隆起を生じます。病気が進行すると、果実が変形したり、落果したりします。また、葉が枯れたり、枝が折れたりすることもあります。赤星病は、病原菌が風や雨によって運ばれて広がります。
症状について

-症状について-
「赤星病」に侵されたナシやボケは、特徴的な症状を示します。葉の裏側に、赤褐色の小さな斑点が現れます。これらの斑点は時間とともに大きくなり、次第に合流して不規則な形をした病斑を形成します。病斑は中心部が黒くなり、回りは赤褐色の縁取りで囲まれています。
病気が進行すると、葉は変形し、しわくちゃになってきます。また、葉の縁が巻き込み、内側にカールします。さらに重症化すると、葉が黄変して落葉してしまうこともあります。果実にも症状が現れ、赤褐色の斑点がつき、変形したり、大きさの成長が阻害されたりします。
病原菌の生態

赤星病の病原菌は、サビキン科に属する菌類です。病原菌は二つの生活環をもち、それぞれ別の宿主植物で生活しています。
第一の宿主であるナシやボケでは、菌は葉の表面に冬越し胞子として冬を過ごします。春になると、胞子が発芽して葉に小さな黄褐色の斑点をつくります。この斑点は時間の経過とともに大きくなり、葉が枯れて落ちます。
第二の宿主であるマツでは、菌は針葉の上で夏胞子として生活します。夏胞子は風によって運ばれ、ナシやボケの葉に付着すると、再び冬越し胞子へと戻り、生活環を繰り返します。
防除方法

赤星病の防除方法は、病原菌の発生源となる落葉の処理、薬剤散布などが重要です。落葉は、病原菌の胞子が発生する場所となるため、定期的に集めて焼却または埋設することが効果的です。また、薬剤散布は、病原菌が葉に侵入するのを防ぐことができます。予防的な散布を繰り返すことで、赤星病の発生を抑制できます。
発生を抑えるための対策

ナシやボケに発生する「赤星病」は、葉や果実に赤い星のような斑点ができる病気です。この病気を抑えるためには、いくつかの対策があります。
まず、病原菌が侵入するのを防ぐことが大切です。剪定や摘果で過密を避け、風通しを良くすることで病原菌の発生を抑えましょう。また、耐病性の品種を選ぶことも有効です。






