植物にとって重要な「温周性」を知る
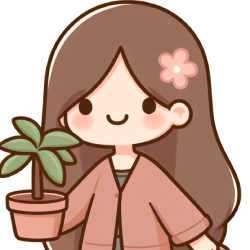
ガーデニングを始めたい
『温周性』について教えてください。

ガーデニング研究者
『温周性』とは、植物が周期的に変化する温度環境下で成長や開花を促される性質です。原産地気候への適応と考えられています。
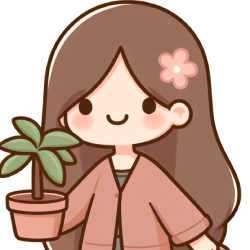
ガーデニングを始めたい
周期の長さによる違いはありますか?

ガーデニング研究者
はい。周期の長さにより、『日温周性』と『年温周性』があります。球根類や宿根草などは、通常、強い年温周性を持っています。
温周性とは。
ガーデニングでよく使われる「温周性」という用語は、植物が一定の温度よりも、温度が周期的に変化する環境の方が、成長、つぼみの分化、開花が促進されることを表します。これは、植物の原産地での気候に適応した結果と考えられています。この温度変化に対する反応を温周性と呼びます。
温周性の周期の長さによって、「日温周性」と「年温周性」に分けられます。多くの球根植物、宿根草、花木は、強い年温周性を持っています。つまり、これらの植物は、一年を通じて気温の変化が大きい環境で育つことに適応しているのです。
温周性の定義

植物の成長には「-温周性-」と呼ばれる特性が大きく関わっています。温周性とは、ある植物が一定温度範囲内でのみ成長できる性質のことです。-特定の植物種ごとに最適温度範囲が異なり、この範囲から外れると成長が阻害されてしまいます。-そのため、植物を育てる際には、それぞれの最適温周性を把握することが重要です。
温周性の種類

–温周性の種類–
温周性は、植物が特定の温度条件に曝されることによって引き起こされる反応を指します。この反応は、さまざまな種類に分類できます。
* -長日植物-長時間の明期を必要とする植物で、それより短い明期では開花しません。
* -短日植物-短い時間の明期を必要とする植物で、それより長い明期では開花しません。
* -中間日植物-長日植物と短日植物の中間的な特性を示し、特定の明期の長さに対して開花する植物です。
* -日中立植物-明期の長さに影響されずに開花する植物です。
* -二形反応植物-環境条件によって、異なる開花の性質を示す植物です。例えば、特定の温度で長日植物として振る舞い、別の温度では短日植物として振る舞う場合があります。
植物における温周性の影響

植物における温周性の影響は、植物の生育に重要な役割を果たします。温周性とは、植物にとって最適な温度の範囲を表し、それより高い温度または低い温度では生育が阻害されます。
最適な温度範囲内では、植物の光合成、呼吸、成長などの生理機能が活発になり、健全な生育が促進されます。しかし、温度が範囲外になると、代謝反応が低下したり、タンパク質が変性したりと、植物に悪影響を及ぼします。
また、温周性と関連する休眠という現象も重要です。休眠は、植物が厳しい環境条件から身を守るための適応です。最適な温度範囲外では、植物は休眠状態に入り、成長や代謝活動を停止させます。休眠から目覚めると、環境条件が改善され、生育が再開されます。
球根類や宿根草の温周性

球根類や宿根草には、温周性という特徴があります。これは、ある一定の温度範囲内で、低温期と高温期を経験することで、休眠と生育を繰り返す性質です。球根や地下茎が、秋から冬にかけての低温期に休眠状態になり、春から夏にかけての高温期に発芽・生育します。球根類では、チューリップやヒヤシンスが温周性植物の代表的な例です。また、宿根草では、オダマキやフウチソウなどが温周性を持ちます。温周性を理解することで、これらの植物の栽培や管理に役立てることができます。
園芸における温周性の活用

園芸において、温周性の理解は不可欠です。温周性は、植物が特定の温度範囲内で最もよく成長する温度の幅を表します。この知識により、栽培者は最適な成長条件を維持し、植物の健全な成長と収穫を促進できます。
例えば、トマトは温周性植物で、昼間の気温が20~26℃、夜間の気温が15~18℃という比較的高い温度範囲を好みます。一方、レタスは冷涼性の植物で、昼間の気温が15~20℃、夜間の気温が5~10℃という低い温度範囲を好みます。栽培者は、植物の温周性を考慮することで、適切な温度を維持し、成長と収穫を最適化できます。






